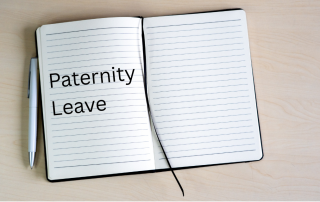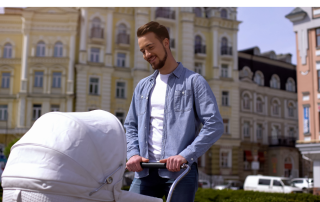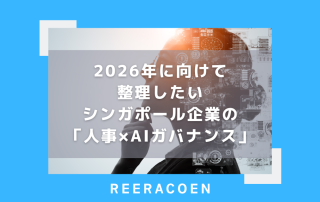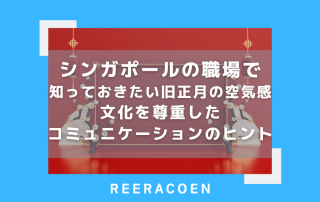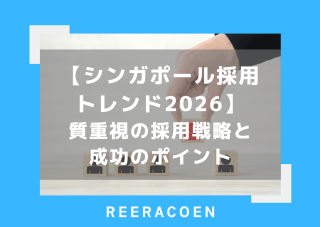シンガポールの父親の育休制度の今

こんにちは。
リーラコーエンシンガポール マーケティング担当の野上です。
オムツ替えから子どもとの絆づくりまで—育児休暇はもはや「あると嬉しい」福利厚生ではなく、ジェンダー平等や柔軟な働き方、そして国としてのサステナビリティを象徴する重要な制度になりつつあります。
昨年2024年、出生率の過去最低を記録した当地では、父親の積極的な育児参加を促すため政府がさまざまな取り組みを進めています。
近年、シンガポールでは企業と求職者の双方において、「親としての役割」に対する意識が大きく変化しています。
柔軟な働き方が広まるなか、家庭で積極的に育児に関わる男性が増える一方、企業側もそうした動きに対応する形で育児支援に力を入れ始めており、父親の育児休暇は先進的な企業文化の象徴として注目されてきています。
そこで本記事では、2025年時点におけるシンガポールの父親の育休制度の最新動向、諸外国との比較、そして企業が今後取り組むべき施策についてご紹介してまいります。
【目次】
1.シンガポールの父親の育休制度:制度の進化と実態
2.企業文化としての課題と今後の展望
3.父親の育休制度:雇用主にとっての意義とは?
4.他国の取り組み:韓国、日本
5.企業が今後取り組みたい、具体的アクションとは
6.最後に
1.シンガポールの父親の育休制度:制度の進化と実態
まずはおさらいを兼ねて、2025年現在のシンガポールでの父親の育休制度について見ていきましょう。
シンガポール政府は、家庭支援とワークライフバランスの実現を目指す「Forward Singapore」構想の一環として、父親の育児参加を後押ししています。
2024年1月1日以降に生まれたシンガポール人の子どもを持つ父親に対し、政府支給による育児休暇が2週間から4週間へと倍増されました。
この取り組みは、家庭における父親の役割を強化し、男女問わず育児に参加できる環境づくりを促進するものです。
取得状況はどうでしょうか。
社会・家族開発省(MSF)の発表によると、2023年の父親の育休取得率は56%と、シンガポールで過去最高を記録しています。
前年の53%から着実に上昇しているものの、依然として44%の対象者が制度を利用していないという現実があります。
取得をためらう理由としては、職場での理解不足やキャリアへの影響を懸念する声が挙げられます。
育休の使い方については柔軟性も確保されており、企業と従業員の合意があれば、子どもの誕生から12カ月以内であれば分割して取得することも可能です。
こうした制度設計により、育児と業務のバランスを取りやすくなっています。
育児支援においては、柔軟な働き方(フレックスタイムやテレワークなど)と併用する割合も増加傾向にあります。
同省によると、2023年にはフルタイム従業員の87%が何らかの柔軟勤務制度を利用しており、前年の84.1%からさらに上昇しています。
こうした勤務制度の整備が、日常の中での育児参加をより現実的なものにしています。
2.企業文化としての課題と今後の展望
このような制度の整備が進む一方で、すべての企業が積極的に対応しているわけではないようです。
職場によっては、育休取得をためらわせる空気や業務体制の不備が障壁となる場合もあります。
このような場合、従業員は人材開発省(MOM)やTAFEP(公正な雇用慣行推進機構)に相談することが可能です。
また、シンガポールは国際的に見れば順調に制度が進んでいる国の一つですが、北欧諸国と比べると、取得期間や職場文化といった面ではまだ改善の余地があります。
今後、制度の活用を一層進めるには、職場文化や企業側の理解の浸透が引き続き重要な要素となると考えられます。
3.父親の育休制度:雇用主にとっての意義とは?
こうした社会全体の変化に対応するうえで、企業に求められる役割はますます大きくなっています。
特にZ世代やミレニアル世代を中心とした若い世代の男性社員は、「家庭と両立できる働き方」や「育児に理解のある職場環境」を重視する傾向が強まっており、これは採用や定着にも大きく影響してくるでしょう。
このため、父親の育児休暇取得を支援する取り組みは、組織における人材戦略の一環として注目されています。
こうした施策は、例えば以下のような効果が期待できます。
・優秀な人材の離職防止および定着率の向上
・多様性を尊重する包摂的な企業文化の構築
・従業員の組織への帰属意識や仕事への意欲の向上
さらに、父親の育児参加が進むことで、パートナーの産後の回復支援や子どもとの愛着形成の促進といった家庭内の効果も期待されるため、結果として家庭と仕事の両立を後押しする環境づくりにつながります。
これらの取り組みは、単なる福利厚生にとどまらず、中長期的な視点での人材確保・活用の観点からも企業にとって重要な施策と考えられています。
4.他国の取り組み:韓国、日本
同じアジアの中でも韓国や日本はどうでしょうか。
まず、シンガポール同様に出生率の低下に直面している韓国では、育児休暇の延長や現金給付といった政策的支援が導入されています。
しかし、職場文化や社会的な期待とのギャップにより、制度が十分に活用されていない現状があります。
多くの男性が、育休取得によるキャリアへの影響を懸念しているためです。
日本は世界でも有数の手厚い育児休業制度を持つ国の一つです。
父親にも最大1年間の育休取得が認められていますが、実際の取得率は依然として17%前後と低水準にとどまっています(※企業による)。
背景には、シンガポールと同様、ジェンダーの役割に対する固定観念や、取得しづらい職場の空気といった文化的要因が考えられています。
その点、シンガポールは制度の拡充と実際の取得率の上昇が並行して進んでいるという点で、非常にポジティブな位置にあります。
課題は「文化的変革」。制度を活かせる風土をどう育てるかが、今後の鍵になるでしょう。
5.企業が今後取り組みたい、具体的アクションとは
制度の有効活用をさらに促進するためには、企業が積極的に社内環境や風土を整備することが不可欠です。
現状の改善方法としては、以下のような取り組みが挙げられます。
・育休取得の「許可文化」をつくる:経営層や管理職が率先して取得を推奨することで、育休が自然に取得できる雰囲気を醸成します
・業務体制の見直し:一時的な不在にも対応できるチーム体制を整えることで、育休取得に対する不安や罪悪感を軽減します
・育児参加を組織文化に組み込む:育休取得者の事例共有や、社内報での紹介、ウェルネス施策への統合などを通じて、父親としての役割を組織として認識する姿勢を示します
・柔軟な働き方と連携させる:すでに多くの企業が導入しているテレワークや時差出勤制度を、育児支援の観点からも再評価し、制度の運用を見直すことが求められます
6.最後に
今回はシンガポールの父親の育休制度の今というテーマでお伝えしてまいりました。
育児休暇の議論は、単に「何週間取れるか」という話にとどまらず、そこには、家族のかたち、働き方、そして社会全体の価値観の変化が色濃く表れています。
企業も、父親自身も、そして社会全体も「育休は家族と仕事のどちらかを選ぶものではなく、両方を支え、より良い社会風土を醸成する手段だ」という意識を持つことが、次の時代のスタンダードになっていくのではないでしょうか。
===============
日系の人材紹介会社リーラコーエン シンガポールは、
シンガポールでのフルタイムやパートタイムでのお仕事紹介だけではなく、あなたに合わせたキャリア構築・面接対策などを無料で承っております。
納得のいく転職を、経験豊富なキャリアコンサルタントが最後までご支援させて頂きます。
シンガポール国内転職・キャリアアップに興味をお持ちの方は、是非お気軽にご相談くださいませ。
★☆最新求人方法はこちらから★☆
また、就労や生活情報など、シンガポールでの時間をより豊かにするための最新情報をブログにてお届けしています。
どうぞお見逃しなく!
シンガポール転職に関する記事はこちらから
シンガポール生活情報の記事はこちらから
シンガポールでの子育てに関する記事はこちらから
またこのブログ内容は、フェイスブックおよびインスタグラムでも配信しておりますので、
是非いいね・フォローをお待ちしております。
>>ついにチャンネル登録者3,500名突破<<<
毎週、シンガポール拠点とその他アジア拠点からお届け!
動画で"海外で働く・生活する"を知る、Reeracoenチャンネル
ぜひチャンネル登録・イイね!を宜しくお願い致します。